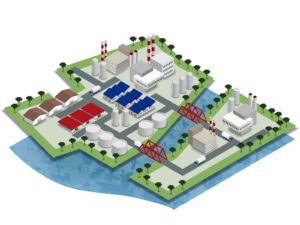国民・再エネ事業者・電力会社それぞれの目線で、FIT制度のメリット・デメリットを整理しました。
目次
国民
国民のメリット
- 燃料代のかからない再エネが増えれば、将来の電気料金が海外の燃料価格に振り回されにくくなり、 電気料金の安定化が期待できる。
- 日本で作れる電気が増えるので、輸入に依存しすぎないため、エネルギーの安全保障につながる。
- 排出CO₂量が下げられるので、温暖化防止や大気汚染等、環境改善に貢献できる。
国民のデメリット
- 再エネ賦課金を負担しなければならないため、電気料金が上昇する。
- メガソーラーでの森林伐採や景観破壊など、乱開発による弊害が生じる。
- 再エネ事業者のために、国民はその差額(再エネ賦課金)を負担を強いられ、不公平感が生じる。
再エネ事業者
再エネ事業者のメリット
- 一定価格で必ず買い取ってもらえるので、事業計画を立てやすい。
- 発電コストが下がれば下がるほど利益が大きくなる。
- 投資家や銀行からの融資が受けやすい(収入が国に保証されているため)。
再エネ事業者のデメリット
- FIT依存体質になりやすく、制度終了後の競争力が弱い。
- 「高値で売って国民に負担をかけている」という批判を受けやすい。
- 開発場所が限られ(山林伐採・景観問題など)、地域との摩擦が増える。
電力会社
メリット
- 再エネを「必ず買わないといけない」義務があるが、そのコスト差額は国民が負担するため、会社として損をしない。
- 再エネ導入量に応じて「国の政策に協力している」アピールができる。
- 再エネの比率が上がることで、将来の国際的な環境規制に対応しやすくなる。
デメリット
- 系統(送電網)の調整コストや負担が増える(再エネは天気で出力が変動するため)。
- 再エネの受け入れ制御(出力抑制など)の手間が増える。
- 「電気代が高くなっているのは電力会社のせいだ」と誤解されやすい。
日本国
日本国のメリット
- 高値での買い取りを保証することで、多くの事業者が参入し、短期間で再エネ発電量を増やせ再エネの普及促進につながる。
- 石油・ガス・石炭など輸入に頼る資源を減らし、自国で賄える再エネの割合を増やせるため、エネルギー安全保障を強化できる。
- 太陽光パネルや風力発電機の市場が拡大することで、メーカー・研究機関の成長につながり、新たな技術革新・産業育成が期待できる。長期的には、国際競争力のある産業に育つ可能性もある。
- CO₂削減に貢献でき、国際的な「脱炭素」の流れに乗り、国際的評価(環境外交)が上がる。特に、パリ協定など国際的枠組みで有利に立つことが期待できる。
日本国のデメリット
- 国民負担が増大する。再エネ賦課金が電気料金に上乗せされ、家計や企業コストを押し上げる。結果として「国民の不満」「産業の国際競争力低下」につながる懸念。
- メガソーラーなどの短期的な普及拡大が、森林伐採などの自然破壊や、景観破壊を引き起こす。
- 地域の反対運動が増加する。
- 太陽光や風力は 天候で出力が変動するため、電気の需給バランス調整が難しくなり、大規模停電リスクが高まる可能性がある。
- 高値での買い取りが長期化すると、国民負担が重くなり、制度の持続性に問題が生じる。実際、日本ではFITの後に FIP制度(市場価格連動型)へ移行しつつある。