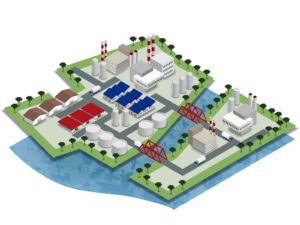CCSは「温暖化対策の切り札」として期待される一方、技術的な不確実性・高コスト・環境リスク・社会的な責任問題が懸念されており、批判的な立場からは「再エネ普及や省エネに投資すべき」との声が強いです。
目次
技術的な懸念
長期的な漏洩リスク
地中や海底に貯留したCO₂が、地震・断層活動・地質の隙間などから数十年〜数百年後に漏れ出す可能性。完全に「恒久的」とは言い切れない。
監視の困難さ
地下深部や海底でのモニタリングは技術的・経済的に難しく、漏洩の検知や責任の所在が不明確になりやすい。
大規模インフラの必要性
発電所や工場から回収したCO₂を輸送・圧入するために、専用のパイプライン・施設が必要でコストや安全リスクが増大。
環境的な懸念
地震・地殻変動の影響
日本のように地震の多い地域では、貯留層の安定性に不安がある。
海洋環境への影響
海底貯留で漏れた場合、海水の酸性化や生態系への悪影響が懸念される。
副次的リスク
CO₂漏出による「窒息事故」(例えばアフリカ・ナイオス湖の自然二酸化炭素噴出事故のようなケース)も懸念材料として引き合いに出される。
経済的・社会的懸念
コストの高さ
CO₂回収・輸送・貯留は莫大な費用がかかり、再エネ投資の方が効率的だという批判がある。
エネルギー効率の低下
CO₂回収設備は膨大なエネルギーを消費し、結果的に発電効率を下げる。
責任の所在
数百年スケールでの管理責任を、企業か政府か誰が負うのか不透明。
政策・倫理的な懸念
化石燃料依存の温存
CCSがあることで「石炭・石油・ガスを使い続けてもよい」という免罪符になり、脱炭素の本質的な解決を遅らせる危険。
実証不足
世界でも大規模商業プロジェクトはごく少なく、多くは失敗や縮小を経験している。
地域住民へのリスク転嫁
漏洩・事故時の影響は地域住民が負うのに対し、利益は企業が得るという不公平さへの批判。